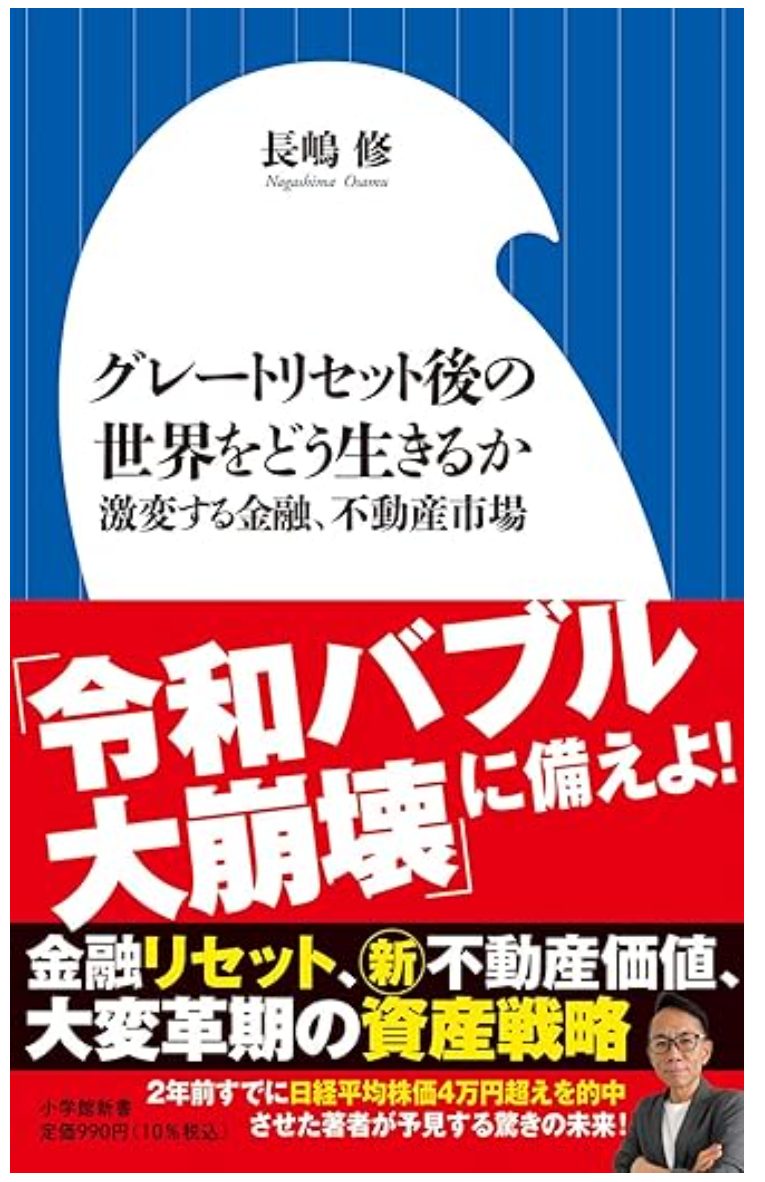『ヒミツ』第11巻 28 連携6
28 連携6
興奮系のドーパミンやエンドルフィンは、一時的に強い高揚感をもたらす。
もちろん、それらも大事なホルモンなのだけれど、
現代文明ではほっといてもドバドバ出てくるから、心配いらない。
問題は、鎮静系のセロトニンとオキシトシンよ。
この2つは、地味に、長続きする。
ジワジワくる小幸せ、日々のゆるぎない自己肯定感、
貢献することの内なる満足感、チームでまとまる安心感、
日常にひそむささやかな喜び、子の寝顔を見るときのあの充足感。
どんなにお金持ちになっても、どんなにすごい人になっても、
どんなにフォロワーが増えても得られない、おだやかな幸せたち。
ささやかな愛と喜び。
それらが分泌されやすい環境を、意識して組織的に作っていくの。
企業風土として。
現代の企業経営は基本成果主義であり、数字を追いかけることはあっても、
ホルモンを追いかけるなんてまずしない。
なぜなら、行き過ぎた金融資本主義の下では、
株主利益こそが最高の価値であり、従業員の幸福なんて
4の次、5の次なんてのが実態だから。
当社の場合は、まったく別のアプローチを取っている。
収益を、「本質的に副産物である」と定義しているの。
社員一人一人が《豊かな自己実現》をするとき、
結果的にそこには「ごきげんな会社ライフ」も含まれているはず。
当然そこには
・給料が高い
・残業は少ない
・休みは多い
・人間関係が良好
・やりがいがある
・自分のしたことに感謝してもらえる
といった要素たちが含まれており、それらが実現されている企業は
必然的に業績が好調であるはず、と考えるの。
つまり、《ゆたかな自己実現》のおこぼれとして、
結果的に招来される副産物が「好調な業績」である、という考え方よ。
筆者の会社では、すべてがこのポリシーの下で運用されているわ。
社員の《ゆたかな自己実現》が先、会社の「好調な業績」は後。